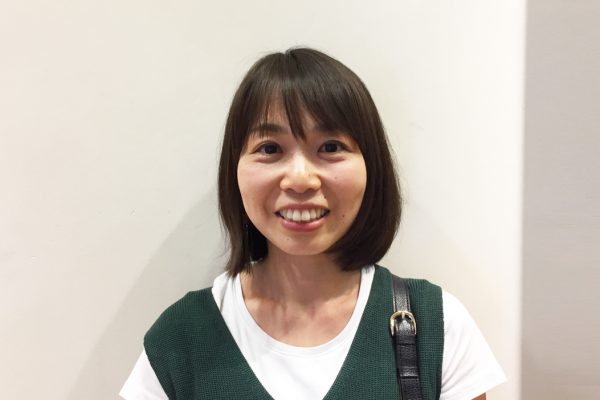この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
体験談のあらすじ
微熱が続いていたものの、保育士補助として責任をもって働いていたため、我慢して仕事を頑張り続けていた高松珠代さん。しかし体調が急激に悪化していき、急性骨髄性白血病の診断が下る。家族のサポート、とりわけ大切な息子からの骨髄移植を受け、必ず元気になると決意した高松さんは、危ない時期を乗り越えて、再び社会復帰を果たした。
5yearsプロフィール:https://5years.org/users/profile/716/
本編
なかなか治らない風邪
神奈川県逗子市在住の高松珠代さん(取材当時54歳、2013年当時50歳)は、保育士補助として横浜市立大学附属病院内にある院内保育園で勤務していた。
院内保育園は、入院治療を続けている子供たちの保育をする施設なので、医療のことも頭に入れて仕事をする必要がある。
たとえば、水分制限がある園児には、その日、水の摂取をひかえさせるよう、目を配る必要がある、といった風に。
高松さんの子どもたちは、3人共、すでに成長して大きくなっており、長女は社会人、長男は大学4年生、次男は大学1年生と、子育てもひと段落したところだった。
とはいうものの、長男はいまだに同居していたし、家事全般は高松さんがこなしていた。
2013年の秋、夜になると微熱が出るようになった。
「働きすぎで風邪でもひいたかな」と思っていたが、年内のシフトはすでに決まっていたので、仕事を減らすわけにもいかず、市販の風邪薬「ロキソニン」や「バファリン」を服用して様子をみた。
しかし、なかなか微熱はひかず、更年期障害を疑ったりもした。
夫から「最近、疲れたというのが口癖になってるよ」と言われた。
ところが、年の瀬も押し迫った12月半ば、車で職場に向かっていたときに、急に眉間の奥がキーンとしびれた。
まるで水泳をしていて鼻に水が入ってしまい、キーンとするような嫌な痛みで頭がクラクラした。
「ナニコレ?!」
不安が広がる。
しかし、病院に行って大変な病気だと言われると怖いので、あえて行かない。
やがて微熱は38度近くなり、高松さんは、近所の婦人科クリニックを訪れた。
若い男性医師から更年期障害のための漢方薬を処方された。
服用すると、一時的に微熱は下がり、頭痛もひいた。
「2週間」という余命宣告
ところが、再度発熱したあたりから、高松さんの体調は悪化の一途をたどり始める。
全身が重たくだるい。
筋肉痛に加えて関節痛もある。
そして気になったのは右脚のふくらはぎに大きな水膨れが出てきたことだった。
やっぱり変だと感じた高松さんは、一週間ほど後に一般内科クリニックを訪れる。
血液検査をしたところ「白血球の数が極端に少ないので、大きな病院で精密検査が必要だ」と言われる。
そして、横浜市立大学附属病院に紹介状を書いてもらった。
診てもらうのに4日待たなければならなかった。
その間、熱は上がり、体調は急激に悪化していた。
血液内科で、「急性リンパ性白血病が疑われるので、すぐに入院してください」と言われる。
具合が悪く、一刻も早い治療を望んでいた高松さんは、ショックよりも「これでやっと治療が始まる」といった、安堵の気持ちのほうが強かった。
一方、付き添ってくれた夫は重い事実を知りショックを受けたようだった。
長男も病院に駆けつけてくれ、夫と3人で医師の説明を聞くことになった。
「精密検査の結果、急性骨髄性白血病とわかりました。このまま何の治療もしないと2週間で死にます」
医師にこう宣言され、夫が泣きだした。
結婚して26年。
初めて見る夫の涙だった。
一方、高松さんは、主治医から明確な説明を受けたことで、治療に対して覚悟を決める。頑張る気持ちが湧いた瞬間でもあった。
長男は、あまりの衝撃からか、黙って面談室を出ていった。
心配した医師が追いかけて長男のフォローアップをしてくれた。
なかなか進まない治療
医師は右脚のおできを「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」だといった。
白血球の数が少ないため、身体の抵抗力が落ち、結果的にできた化膿性炎症なのだという。ただ、もしいま抗がん剤治療を行い、骨髄芽球をたたくと、正常な白血球がさらに減って抵抗力が一層弱まってしまうので、まずは抗生剤を投与して蜂窩織炎の治療を優先することになった。
余命2週間の白血病だとわかっていても、その治療ができない事実に高松さんはがっかりした。
結局、抗生剤投与はその日から年明けまで行われた。
年が明けて2014年1月2日。
蜂窩織炎は完治していなかったが、見切り発車的に抗がん剤治療(寛解導入療法)の開始となった。
ダウノマイシンとAra-C(キロサイド)を7日間投与する。
抗がん剤薬の副作用はきつかったが、そもそもの白血病による症状がすでにかなりきつかったため、高松さんは、副作用をさほどきついとは感じなかった。
その後、高松さんは、隔離された無菌室に入ることに。
結局、18日間、隔離される状態が続いた。その間、家族が見舞いに来てくれたが、無菌用のガウンとキャップを着用して、1人ずつ、しかも短時間しか会うことができない。
それでも嬉しかった。
退院後、自宅に戻ってホッとしたものの、この1カ月で体力は随分落ちてしまっていた。
また、この病気は、寛解したとしても、多くの患者が再発するということで、寛解後療法(地固め療法)として、2倍量の抗がん剤投与が待っていた。
息子というドナー
寛解後療法より体は楽になってきたが、身体が楽になると今度は精神的にふさぎ込むようになった。
がん患者は体調がよくなるにつれて心が明るくなるという単純なものでないときがある。
本当に体調が悪いときは、不安になる精神的余裕すらないからだ。むしろ、休薬中とか、体調が改善したときに、初めて心に余裕ができて、よくないことを考えだすことがある。
この時の高松さんは、まさにそれだった。
急性骨髄性白血病は、骨髄移植の骨髄提供者が現れない限り、寛解後療法を続ける可能性があるのだ。
いつまで続くのかという不安が生まれた。
そんなとき、2人の息子にその適応があることがわかり、長男がドナーとして骨髄を提供してくれることになった。
高松さんはゴールデンウイーク後の5月9日に入院し、CVカテーテルを首に取り付けた。
さらに、全身への放射線治療をし、高松さんの体にある血液細胞を徹底的に叩いて破滅させた。
これは、血液の入れ替えを行うための前準備だった。
そして、骨髄移植をする5月21日。
長男から抜かれた800㎖分の骨髄液のビニールパック3つを見て、高松さんの目から思わず涙があふれ出た。
「こんなに大量の骨髄液を抜き取るなんて……」
息子に取り返しのつかないことをしてしまったと思い、自分を責めた。
3時間かけて、首に取り付けられたCVポートに骨髄液が注がれた。
自らの骨髄液を提供して母を助けようとしている長男、心から心配してくれている長女、次男、夫に思いを馳せ、「提供された骨髄液の一滴も無駄にせず、必ず元気になる」と心に誓った。
2つめのパックから骨髄液を入れている途中、長男が点滴棒を押しながら無菌室に入ってきた。
母親に自分が元気なところを見せたくて顔を出したという。
高松さんは、フラフラと椅子に座り込む息子を見て、胸が熱くなった。
造血幹細胞移植は無事に終了した。
目立った拒絶反応も起こらず、家族全員で安堵した。
しかし、6月に入って、再び問題が発生する。
骨髄移植の不適合ではなく、移植治療の前処置の段階で起こった合併症が出たのだ。
これが思いのほか重篤化し、集中治療室に2週間も入院することになる。
食事をとることもできなくなり、身体はどんどん弱る。
意識を失ったことも数回あった。
「せっかく息子に命を助けてもらったのに……」
そう思いながら厳しい日々を一日一日繋いでいた。
どん底からの生還
骨髄移植のための入院から2ヶ月半が過ぎた8月初旬、高松さんは、ようやく退院することができた。
自宅に戻った高松さんは、体力も筋力もすべて失ってしまい、ヨロヨロだったが、人生のどん底からゆっくりと這い上がっている感じがして、嬉しかった。
夏の間、家にいることが楽しかった。周囲のすべてが素晴らしい世界に見える。
新しくもらった命……。
「自分は今、1歳なんだ」と感じた。
それから3年後の2017年6月。
体力も随分戻り、自分にも何かできないかと考えるようになった高松さんは、昔の職場の特別支援養護学校に連絡した。
すると、職員不足で困っていた同僚から大歓迎され、教員として採用が決まった。
週2日間の非常勤教員として、昔の職場に戻ることになった。
自宅から電車を乗り継いで1時間ほどの通勤だが、途中、かつて入院していた横浜市立大学附属病院がある。
「前はこの駅で降りて病院に通っていたけれど、今は通り過ぎて職場に向かっている」
その事実が、苦難を乗り越えた“今”を感じさせてくれるのだった。

高松珠代さんの詳しい「がん闘病記」、及び「インタビュー記事」はウェブサイト『ミリオンズライフ』に掲載されています。ぜひ、読んでみてください。