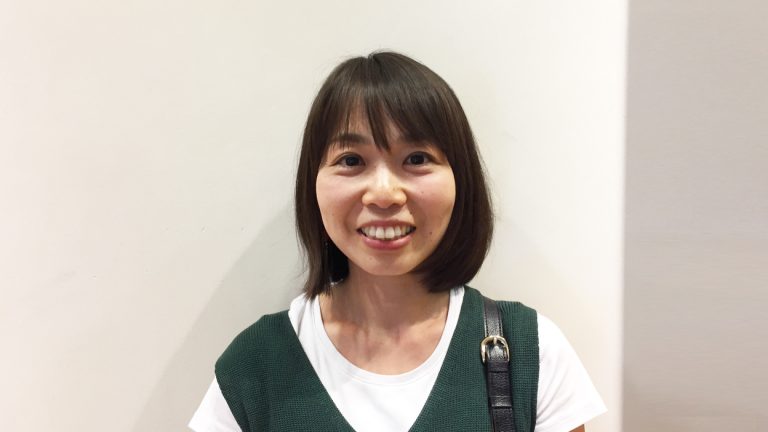この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
体験談のあらすじ
仕事も家庭も充実していた柳沼明日香さんの卵管がん(ステージ3c)がわかったのは、第二子の妊娠時だった。夫婦で苦しい時を乗り越えて、がんを治し、家族の時間を取り戻した柳沼さんの闘病記を紹介する。
本編
東京都大田区在淳の柳沼明日香さん(2015年当時35歳)は、2015年に第二子を妊娠した。結婚して4年ほどなかなか赤ちゃんが授からず、やっと生まれた長女は2歳になっていた。
「奇跡だ!また、赤ちゃんを授かることができるなんて!」
家族が増えることを望んでいた柳沼さんにはうれしくてたまらなかった。
ところが、長女の時と異なり体調が優れなかった。
便が出ない日が3日以上続き、便意すら感じない日もあり、頻繁に尿意をもよおした。そして、へその右下付近の腹部が、ポコッと腫れていた。うつぶせになると下腹部に違和感があるように感じたが、便秘のせいかもしれないと思った。
妊娠時に卵管がんの告知
2015年1月31日、産婦人科へ向かった。すでに悪阻(つわり)が始まっていた。
医師に症状を伝えると怪訝な表情を浮かべた。
これは便秘ではなく卵巣が大きく腫れており、おそらく手術をしなければならないと説明された。
一通り調音波(エコー)で調べた医師は、東京慈恵会医科大学附属病院本院で精密検査をするようにと初診予約を取ってくれた。
2月4日。東京慈恵会医科大学附属病院に行き、再度超音波検査を行った。
赤ちゃんの心臓が動いているのが分かった。すごくうれしかった。でも気になることがあった。医師は一度も母子手帳をもらいに行くようにとは言わなかったのだ。
次の検査を行うまでの間、赤ちゃんはどうなるのだろうと柳沼さんは怖くてたまらなかった。
命の優先順位
経膣(けいちつ)超音波検査を行ったところ、卵巣が13センチくらい腫れており、手術が必要なことを知らされた。
悪性の可能性があり、これからレントゲン検査、血液検査をして腫瘍マーカーを調べ、妊娠しているがMRI検査も行うことになった。
「悪性の可能性…」
柳沼さんは思い切って赤ちゃんはどうなるのか質問してみた。医師は驚いたような顔をしたがはっきりと言った。
「もしも、分娩できることになったら、その時は優先してあげますから。まずはあなたの命です。」
出産で頭がいっぱいだったはずのが、医師の一言で柳沼さんの心の中は「分娩」よりも「悪性」という言葉が大きくなっていった。
2月6日、柳沼さん夫婦に検査結果を伝えられた。
腫瘍マーカーCA-125(基準値35U/ml以下)が2000を超えていた。
大変なことが起こっていると恐怖で体が震えた。
閉経前の女性は、妊孕性(にんようせい)温存といって子宮などを残すが、柳沼さんの場合はすべて摘出した方が良いと言われ、腫瘍の摘出のため中絶しなければならないと説明された。
「中絶の勧め…。うそでしょ!」
苦悩の決断
人生で初めての恐ろしい衝撃だった。
体が硬直し、頭が混乱するなか、絞り出すように声で、
「先生、赤ちゃんは諦めます。上の子のためにも、少しでも長く生きたい」
とても重く、つらい決断だった。
柳沼さんは、この日を境に“死”を意識するようになった。
自身の体のことや娘の未来、全てのことが信じられず悪い方へ流れていくようだったが、日常を過ごせるように努力した。
ただ、娘の小さな背中や笑顔を見ていると、涙が止まらなかった。
35歳で癌になってしまい、小さな娘を母親のいない子にさせてしまうかもしれないことが辛かった。
中絶手術の前日。
夫と一緒にお腹の赤ちゃんに「ごめんね」と「ありがとう」とお腹をさすって対話した。
この子は、私に病気のことを命がけで教えてくれた。
柳沼さん夫婦は涙を流しながら手をとりあった。
こんなつらいことは今まで経験したことがない。
赤ちゃんの生きた証は、産科の医師が撮影した超音波(エコー)の写真のみだった。
ご主人は涙でぐしょぐしょになりながら写真の中の赤ちゃんに語りかけていた。
赤ちゃん…、ごめんね、でも本当にありがとう…。
2月20 日、中絶手術を受けた。
手術と喪失感
心配した実家の両親や夫が付き添いたいと言ってくれたが、これ以上迷惑をかけたくないとかたくなに拒み、柳沼さんは一人中絶手術に向かった。
手術が終わった柳沼さんは麻酔薬の影響で吐き気・頭痛と闘っていた。
起き上がることもできず、自宅に着くと激しく嘔吐した。
翌朝、体調は戻ったが、それまであった“つわり”も無くなっていた。
「(おなかの赤ちゃん)本当にいなくなっちゃったんだ…」
柳沼さんは、深い喪失感と未来への強い不安を感じた。
2015年3月5日、腫瘍摘出手術の日。
腹部のリンパ節が腫れているため、手術中にリンパ節の一部を切除してから病理診断を行い、悪性だった場合はすべてのリンパ節を郭清する。
手術は7時間にも及び、中絶手術時と同じく、吐き気と頭痛でなかなか離床できなかった。
手術から8日後、柳沼さん夫婦は主治医から卵巣ではなく、卵管が原発であること(漿液性腺癌)、大傍動リンパ節に転移があり、進行ステージは3cに確定したことを知らされた。
長期にわたる抗がん剤治療
今後はまだ身体に残っている目に見えない癌を叩くため、卵巣がんの標準治療であるTC 療法(パクリタキセル+カルボプラチン)に分子標的薬(ベバシズマブ(アバスチン)を併用して抗がん剤治療を行う。
これを6クール行い、その後、アバスチン単剤を22クール継続投与するという方法で、前向き観察研究というものだった。
全工程が84週間という長期間に及ぶ抗がん剤治療になり、副作用は個人差が大きいため、不安を抱えながらも完治させるため積極的に受けることにした。
手術後、主治医から外泊を勧められ3日だけ自宅に帰ることになった。体力がない状態では家族の負担になるのではないかと不安だった。長女は久しぶりの母親への戸惑いがあり、どこかよそよそしい。
「病気になった自分なんて、家族のお荷物なだけじゃないか…」
柳沼さんは寂しく感じた。
翌日から抗がん剤治療が始まった。
第1クール目の初日は点滴によりパクリタキセルとカルボプラチンを投与。
その夜から倦怠感と関節の痛みを感じたが、3日目にもなると副作用はかなり和らぎ、無事初回投与を終え、1カ月弱の入院生活が終了した。
2クール目以降は3泊4日の短期入院で抗がん剤を投与し、2週間自宅で回復に充てるものに替わった。
このクールから予定通り「TC+アバスチン」に切り替わる。
家族に支えられて
抗がん剤治療の第1クールを終了して2週間が経ったころから、髪の毛が抜け始めた。
わかってはいたが、やはり実際に脱毛が始まるとつらい。まつげや眉毛が抜けると人相も変わり、美容の悩みも出てきた。
娘との入浴も、脱毛用帽子をかぶった。
5月13日から第3クール、6月3日から第4クール。
髪の毛はすっかり抜け落ち、吐き気や立ちくらみといった症状があり、時々風邪も引いた。
柳沼さんは、抗がん剤治療を繰り返し、多くの気持ちを抱えながら毎日を乗り越えていったが、6月に入ると薬による骨髄抑制がきつくなり、休薬期を経てもなかなか血液中の好中球等の値が回復しない。
医師は第5クールの開始予定を遅らせると同時に、今後は薬の量を減らすことを決めた。
抗がん剤の投与が8月1日で終わり、ご主人と一緒に帰宅すると、娘がひまわりの花束を持って玄関で出迎えてくれ、嬉しい区切りの日となった。
その後撮影したCT画像検査では、癌の影はなく、腫瘍マーカーCA125(基準値35U/ml以下)も1桁まで下がり落ち着つく。
前向き観察研究は、「TC+アバスチン」の治療6クールのあと、さらにアバスチン単剤の治療22回が予定された。
“日常”の大切さ
引き続き通院型で治療は続くも、家に帰ってこれたことは、かけがえのない“日常”を取り戻していく上で大きかった。
ついこの前までは、雲の上の世界に吸い込まれてしまうのではないかと思っていたが、今は本来の世界に戻ってきたような実感があり、幸せだった。
2016年7月13日、前年の8月から始まったアバスチンの継続投与が終了し、長期にわたる治療をすべて終えた。
そして、いま……。
毎朝、娘を保育園に送り出し、満員電車に揺られて職場に向かう。
職場に着くと同僚と仕事をし、夕方、娘とともに帰宅して家事をこなし、時には家族で遠出をする、病気前の忙しい日常に戻っている。
当たり前のことなんて何一つない。
病気になる前と病気になってからでは、人生観がすっかり変わっている。
お世話になるすべての人、物に、そして命をかけて病気を教えてくれた赤ちゃんに感謝し、今、幸せな時を過ごしている。

柳沼明日香さんの詳しい「がん闘病記」、及び「インタビュー記事」はウェブサイト『ミリオンズライフ』に掲載されています。ぜひ、読んでみてください。