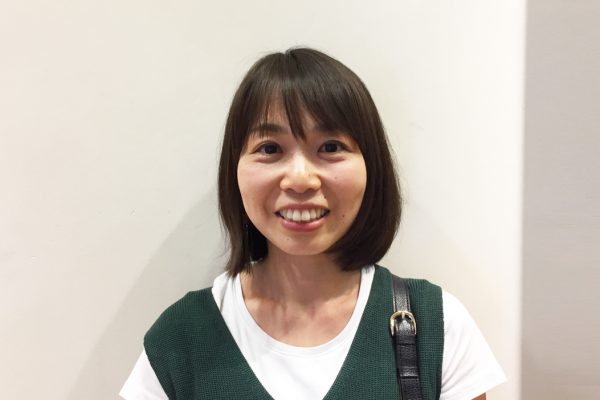この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
体験談あらすじ
柴谷健さんは、高校生だった16歳のとき骨肉腫を発病、左脚切断の手術を受ける。以来、“障がい者”というレッテルに苦しみながらも懸命に社会に溶け込もうと努力していた。そんな頃、理解ある妻に出会い、義足テニスの普及という、新しい目標が見つかる。
5yearsプロフィール: https://5years.org/users/profile/275
本編
成長痛ではない痛み
36年前の1980年・秋、兵庫県で高校生だった柴谷健さん(発症当時16歳、取材当時52歳)は、左足のひざ下のジンジンとする痛みに悩まされていた。成長痛かと思ったが、近所の人に病院に行くようすすめられ関西労災病院の整形外科に行った。
病院では入院して行う「試験切開手術」をすすめられた。
“入院”と“手術”という言葉に柴谷少年の不安はつのった。
12月中旬に「試験切開」のため入院し、無事、手術は終了した。
ところが、それから3日目に突然、千葉大学医学部附属病院に移ると言われた。
千葉県には、放射線総合研究所で医師をしている叔父さんがいた。
翌日、その叔父さんが関西労災病院の病室にまでやってきて、自分の病気は「骨髄炎(こつずいえん)」であることを伝えた。
その後、千葉大学医学部附属病院に転院し、点滴による治療が始まった。
しかし、その日の夕方、吐き気がして食べた夕飯を全部吐き出してしまった。
後から知らされたが、点滴の中身は「メソトレキセート」「アドリアマイシン」という抗がん剤だった。
1981年1月。抗がん剤治療とは知らないまま点滴は続いた。
1カ月に及ぶ治療だった。
抗がん剤治療が終わり、2月に入ると放射線医学総合研究所に転院。叔父さんが担当医となった。
この病院では週に5日間、1日30分程度の放射線治療が行われた。
僕の病気、がんじゃないの?
2月のある日、入院病棟の談話室で他の患者たちと『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ我が子へ』というテレビドラマを観ていた。
実話に基づくドキュメンタリーで主人公の男性が「骨肉腫(こつにくしゅ)」を患い、妻のお腹の中にいる自分の子供を見ることなく他界するドラマだった。
当時、5年生存率は10%以下と言われていた病気だった。
「僕の病気、これじゃないの?」
主人公の症状も受けていた治療もすべて似ていた。
柴谷さんは叔父さんに「僕の病気、骨肉腫じゃないの?」と聞いた。
「大丈夫さぁー」いつもの調子で笑いながら叔父さんは言ったが、明らかに不自然だった。柴谷さんは不安になった。
3月に入るとまた転院。今度は千葉県がんセンターに転院することとなった。入院病棟には同じ世代の10代の患者たちが大勢いた。
同世代に囲まれ今まで感じていた孤独感が和らいだ。
病棟にいる骨肉腫の患者たちの多くは肺にがんが転移し手術を行っていた。
その子たちに比べれば、自身の病状はそこまで悪い状態ではないと思い、希望を持ち始めた。
入院して以来、高校の友人たちが毎週のように授業ノートのコピーを千葉の病院に郵送してくれた。夏休みには、友人二人が兵庫から千葉まで見舞いに来てくれた。
友人たちとの再会、学校復帰への思いが、治療を頑張る強いモチベーションになった。
また、病院内には同世代の仲間たちがいるから安心できるのだが、入院病棟はとても怖かった。同志である10代の患者たちが手術を受け、片足や片腕になって戻ってくるのだ。
「もしかして次は、僕なのか…?」
考えるだけでも怖くてたまらなかった。
成功しない人工関節手術
そして抗がん剤治療が5カ月目となった1981年7月。
柴谷さんは、当時日本で2例しかない人工関節を入れる手術を提案された。
切断ではなく、人工関節?!
足を残せるなら人工関節手術でもなんでも受け入れてやる!
柴谷さんは希望を持ち、再び千葉大学医学部附属病院に移って、人工関節の手術を受けることとなった。
しかし、問題が起こる。
手術のために切開した皮膚が2週間たってもふさがらないのだ。
その2週間後、左足の甲から皮膚と血管を切り取り、左脚の患部に移植する手術を行ったが、それでも切開した個所はくっつかない。
切開した個所がふさがらず一日中つらい痛みが続く。
あまりにも痛くて、たまらずにモルヒネを打つが、薬が切れると痛みを感じ、毎日モルヒネを打つようになった。そのせいか、字がかすんでよく見えなくなってきた。
結局、2度目の移植手術も失敗に終わった。
体力も精神力も限界に近づいていた。
医師から3度目の手術を提案されたが……、
9ヶ月間にも及ぶ入院治療。抗がん剤全身化学療法、放射線治療、抗がん剤全身化学療法、人工関節手術、2度の移植手術、そして毎日モルヒネを打たれる生活……。
もう疲れ切っていた。
この状況から少しでも早く抜け出したかった。
「先生、ぼくの左脚を切断してください」
医師に伝えた。
とても重い決断だった。
自然と涙がこぼれ落ちた。
手術が終われば「身体障がい者の世界」に移ることになる…。
「身体障がい者」としての人生
1981年10月。この日のことは忘れられない。
柴谷さんは左脚を失った。
病室で目が覚めると、左脚がピリピリした感じがし、まだ脚があるようだった。
でも、あるかどうか怖くて確認できない。
この時から自分の脚を見ることができなくなった。
年が明け1982年1月。
兵庫県から茨城県へ引っ越した。
そこが退院後の拠点となる。
2月からは月2回の通院による抗がん剤治療へと替わった。
結局、この1年間は一度も学校に通うことなく終わったため、留年してもう一度高校2年生をすることになった。
親に負担をかけずにいろんな所に出かけたいと思い、原付バイクの運転免許を取りに行った。
茨城県の公安委員会に行くと「片方の脚がない人に免許証を渡すのは無理です」と断られたが、条件付きで試験を受けることができた。原付バイクの免許を得たことで、柴谷さんの行動範囲は一気に広がった。
柴谷さんが一番嫌だったのは、自分が“身体障がい者”であることだった。
途中で切断されてしまっている自分の左脚は、母親を含め家族の誰にも見せていない。自分ですらまだ自分の左脚の状態を確認できなかった。
障害者手帳を見るたびに悔しさがこみ上げる。
自分が障がい者だと実感するだけでなく、入院時代のことを思い出すことも嫌だった。
障がい者でもいいのかな?
高校は何とか卒業できたが、休みがちで学力も劣っていたので2年間浪人し、大学の建築学科に進学した。
1986年4月
大学への入学手続きに健康診断書が必要となった。診断書には「骨肉腫」と書かれていた。
改めて自分の病名が「がん」だったことをこの時知った。ショックだった。
在学中、周りに左足がないことは伝えなかった。
左足がないのはコンプレックスだったし、障がい者だと同情されるのが嫌だった。
大学卒業後、都内でも有数の建築事務所に就職し、充実した社会生活を送る。
だが、入社後も左足のことは隠し続けた。
そして、10年後の2000年、フリーの建築士として独立した。その翌年、後に最愛の妻となる玲子さんに出会った。
思い切って、彼女に「左大腿部(ひだりだいたいぶ)切断」と書かれている身体障害者手帳を見せたところ、
「なんだ、それなら早く言えばいいのに。嘘をつくのはつらかったでしょう」
と、彼女は驚きもせずに言った。
「障がい者でもいいのかな…?」
彼女の言葉を聞いて、これまで「自分は障がい者だ」と考えていたことが意識過剰だったのかなと思うようになった。付き合い始めて3カ月目、二人は結婚を決めた。
2002年11月の結婚披露宴では「二人三脚」というプロフィールを参列者たちに渡し、自分には左脚がないことを初めて公にした。もう隠さなくていいと思うと気持ちが楽になった。
夏には半ズボンをはくようになり、義足を脱いでプールに入るようにもなった。毎年二人でハワイに行くようになった。
2008年、柴谷さんにとって、もう一つの素晴らしい転機が訪れる。
左足を失ってからは敬遠していたが、柴谷さんは幼少のころテニスをしていた。
思い出して、久しぶりに奥さんと打ち合うことにした。
このことがきっかけで、テニススクールに入会し、プロテニスコーチをしている中川勝就さんから「脚があろうとなかろうと、私についてきなさい」と言われ、テニスに夢中になった。
障がい者テニス大会を見に行くと、義足でテニスをしている人達がいた。その姿に柴谷さんは勇気をもらい、テニスにどんどんのめり込む。
パラリンピックでは車いすテニスのみで、義足テニスは含まれていない。
今、義足の人たちが立位で行うテニス大会を作ろうという動きがある。柴谷さんも実現のため、多忙な日々を送っている。
50歳を超えて、自分を支えてくれた人たちへの感謝も日に日に大きくなっている。
人は支えあって生きているのだということを、改めて実感している。

柴谷健さんの詳しい「がん闘病記」、及び「インタビュー記事」はウェブサイト『ミリオンズライフ』に掲載されています。ぜひ、読んでみてください。